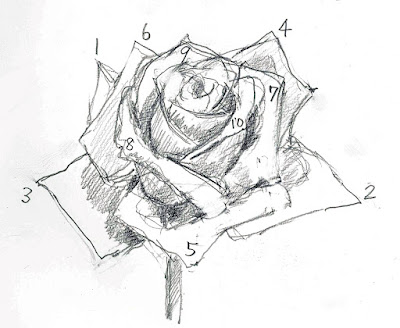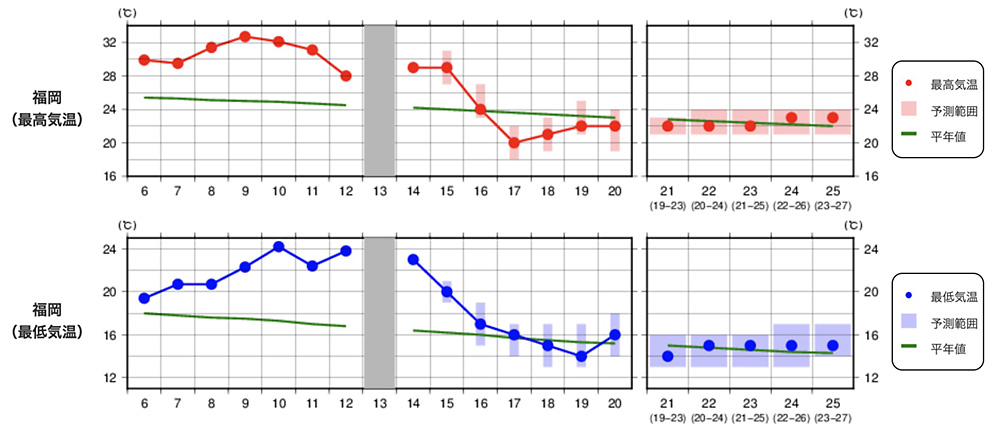福岡バラ会を退会した。バラ栽培を続けるかどうかも含めて、ぼんやりと今後を考える中で、ふと6年前に書いたものを思い出した。2015年11月5日の記事:「師匠から学ぶこと」 それを再掲載して今後を考えるヒントにしたい。書きながら考え、読み返しては書き直すことを繰り返すので、論旨は滅茶苦茶で、結論がどうなるのかもマジ不明。
なお、引用文中の「小林先生」とは、北九州市のグリーンパークバラ園・技術顧問の小林博司先生(写真)のこと。
真理は瑣末な事象の中にある
1 「ユニーク」であることが高く評価される世界
私が写真学生だった頃、その勉強は撮影や現像処理など写真技術の実習と、写真理論(化学・光学)や写真史、表現論などの講義が並行して進められました。中でも重要なのは、自分の作品を作りそれを先生や仲間に批評してもらうことです。そのようにして技術の習得と同時に思考や感性を鍛えながら、自分の世界観や表現方法を確かなものにすることを目指していきます。それらはいずれもユニークであることが高く評価され、この写真学校からは気鋭の若手写真家の登竜門である「木村伊兵衛賞」やベルリン映画祭のドキュメンタリー部門で受賞するなど、優れた映像作家が輩出します。
2 「定型」から入る世界
卒業して10年後、私はある文化教室で写真の講座を担当していたのですが、そのとき隣の部屋で「生け花教室」が開かれていました。ひとつの生け花に何時間もかける様子を垣間見て『これは自分の眼を鍛える良い方法かも』と思い、その教室に入門しました。
その流派は伝統と格式があり指導方法も確立しています。そこでの「お稽古」は私にとっては写真学校とはまるで違う意外なものでした。与えられた花材と花器で、決められたとおりにしなければなりません。「自分なりに」という個性の余地のまったくない、まさに「お稽古」です。これは私にはおもしろくない苦行で、それでも2年近くは続けたでしょうか、ついに我慢できなくなって花鋏をカメラに持ち替えました。以来その流派の作品を今も撮り続けていますが、私と同じ頃に入門したお嬢さんたちは、数十年後の今はすばらしい作品を作る華道家になり、多くのお弟子さんを指導してあります。
日本の伝統文化の中には「道」という言葉がつくものが幾つかあります。生け花は「華道」ですし、その他にも「茶道」や「仏道」あるいは「柔道」というのもありますね。これらに共通するのは「学びは、型から入る」ということです。「長期間お稽古や修練を続ければ自ずとある境地に達する」という考えでしょう。バラの栽培は?「園芸」という言葉はあるけど「道」とは言いませんね。
小林先生は「バラの栽培は楽しく。楽しくなければやる意味が無いよ」とは言われても、それ以外は栽培技術に関する話と実習で、「観念論」めいたことは口にされません。
講座の最初に先生はこう言われました。
バラの栽培方法についてはいろんな考え方があり、ガイドブックの類もたくさんあるけど、このGPバラ園のようにバラを咲かせたいと思ったら、これから講座で私が話すようにやってみてください。
これは「型から入る」ということです。多くの受講者のみなさんにとってそれは苦行ではないし、むしろ楽しくてしかたがないというのは、なぜでしょう?
「定型」の中の自由な精神世界
「定型から入る世界は没個性で非創造的、面白くない苦行」と当時の私には感じられたが、でもそれは正しくない。
初心者が与えられた花材と花器で定められたように花を活けるとしても、そこにキラリと輝く作品が生まれることがあるのも事実。また生花には「格花(かくばな)」 =「お生花(おせいか)」と呼ばれるジャンルもあり、これには厳格な約束事があってそれから逸脱することは許されないのだが、研鑽を重ねた作者が活ける「格花」には、植物の命が際立ち、その背後に作者の個性とその世界観が見える。それに触れると思わずこちらの背筋がシャンとなるような "柔らかな、清々しい緊張感" がある。「定型」そのものと思えるものにも、その中には自由な精神世界が広がっているのだ。
さらに言えば、優れた表現からは作者の存在が消え、花そのものだけが見える。それを「美」と言ってもいいし、「真理」あるいは10/20の記事で触れた 池坊専好(初代)のように「ほとけ」と呼ぶこともできる。
バラの栽培を学ぶこと、特にコンペティション・ローズ(競技バラ)の場合は、この「定型から入る世界」だろうと思う。「出品規定」があり、審査も同じような基準で行われる。
どうだろう、バラのコンテスト会場に並んだ花の中に、作者の精神世界、あるいはそれを超越した「ほとけ」が見えるだろうか。
バラのコンテストは『ゲーム』なの?
福岡バラ会に入ったばかりの6年前の秋、先輩のFさんやEさんに対し、「コンテストはつまるところ、バラの栽培技術の優劣を競う "ゲーム" なんじゃないですか?」と質問したことがある。言外に、『そんなものはつまらない』というニュアンスをモロに出しながら。身の程知らずの、実に生意気な新入会員だった(笑)。
その後5年間、 コンペティション・ローズの栽培に熱中してきたが、私は「栽培技術の優劣を競う "ゲーム"」というレベルを超えることができないまま、ついに "Game Over" になってしまった。正確に言えば、自分で幕を引いた。
「この花でももの足りない バラ作り50年の試行錯誤」を読む
この本は、石橋 五夫、伊加利 勝唔、矢澤 實 の3氏による共著(2016年 ファイン ローゼズ発行)
お三方ともこの世界で素晴らしい実績のある、いわゆる"大御所"。タイトルの「この花でも」という部分に、これまでやってこられた栽培の実績や、その自信の程が窺える。その方々が「この花でももの足りない」と思われているということに、少なからず驚かされた。
なぜ『もの足りない』と思われるのか、何を目指そうとしてあるのか、何度か読み直したけれど、残念ながら私にはその片鱗すらもわからなかった。私が想像できたのは、この世界が既に完結した過去のものではないということと、そして、もしかしたらそれは教えてもらうことではなく、自分で探すことなんじゃないかということ。
この本のP79「終わりに」で、伊加利さんが次のように書かれている。
ここに書かれたことを一から十まで実行なさっても、あなたの花は諸先輩と同じか、ひとまわり小さい程度にしか咲きません。先輩の言を常に批判的に摂取し、ご自身の庭で試してみて、その成果をご自身の目で確かめる、そして、そこに何かを加えてゆく、そこにバラづくりの進歩があります。このような工夫と努力を重ねた方が、次の会長杯を手になさることでしょう。
そうなんだろうな、伊加利さんのご意見は正論と思う。この文章の初出は30数年前の日本ばら会の会報「ばらだより」。その後の日本ばら会は伊加利さんが期待されたように「進歩」したのだろうか、どうなんだろう。
『バラはやっぱりガーデンローズ』
このお三方と同様にこの世界で "大御所" とされる別の方(お名前は伏せる)からは、意外な話を聞いたことがある。
大きな二つの花瓶に、競技花のHTとフロリバンダやシュラブ(いわゆるガーデンローズ)を分けて、それぞれ盛り沢山に生けてあって、どちらも素晴らしいバラ。栽培者は未確認だが、HTはご本人で、ガーデンローズはお弟子さんかも。その二つを見比べながら曰く、『バラはやっぱりこっちだよね』
どちらを選ばれたと思います?
選ばれた方は目に染み入るような美しさだった。今思い返せば、その瞬間に私の中で微妙にスイッチが切り替わったような気がする。その時は意識できなかったけど、それからは「ミニチュア盛り花」や「デコレーション」の部門にも出品するようになった。
真夏のハウスで水やりを続けたことも、これが "ゲーム" であるならば、虚しい結果に終わってしまったことになる。「バラのコンテストは、単に栽培技術の優劣を競うゲームではない」と信じたいが、では何を目指しているのか?
いや、これはコンテスト自体や他の栽培者のことではなく、自分の問題。福岡バラ会での6年という時間を経て、「バラを栽培することに何を求めているのか」という原点に再び舞い戻ってしまった。
3「真理」は既にそこにある
昔読んだ「禅」に関する本に、次のような話がありました。
厳しい修行をする禅寺で、多くの修行僧に供する食事のために野菜を育てている人がいました。その人も僧なのですが、下肥を汲んで肥料にするのも彼の役割です。その僧が何を考えていたのかはわかりませんが、文章の前後から、「他の修行僧のために」とか「これが修行だから」というようなことではなさそうです。その禅寺で一番偉い僧が、野菜を育てている僧を「あの方も立派な禅者」と、若い修行僧を諭します。
私は思うのですが、バラ栽培の本質、美、真理 あるいは 悟り、言葉は何でもいいけれど、小林流に言えば
「バラ栽培の楽しさ」は、長期間の「お稽古」や「修行」をしなければ得られないものではなく、野菜を育てているこの僧のように、今の私の 日々の小さな出来事や作業の中に既にある のではないか。
「学ぶということはそれに気づくこと」だとしたら。。